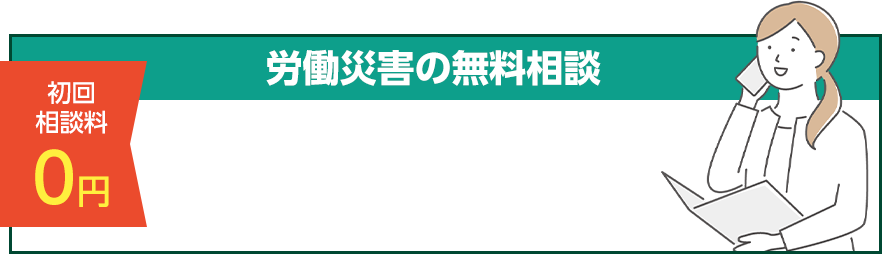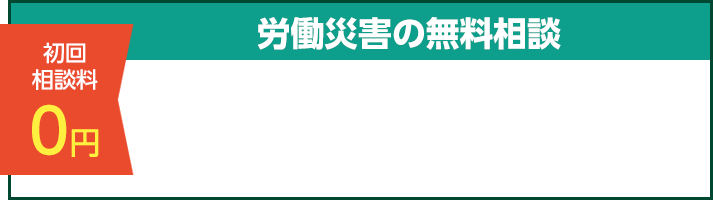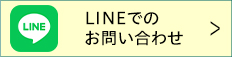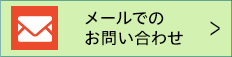労働災害によって負ったケガや病気が、治療を続けても元の状態まで回復せず、後遺症が残ってしまったという方へ。
そのような場合には、「後遺障害」として労災保険による補償を受けるための手続きを行う必要があります。
適切な補償を受け取るためには、労働基準監督署による後遺障害等級の認定を受けなければなりません。
「後遺障害」とは
労災事故によるケガの治療を続けた結果、これ以上の回復が見込めないと医師が判断した場合、その状態を「症状固定」といいます。
この時点で、原則として労災保険からの治療費の支給は終了します。
しかし、症状固定後も身体に障害が残っている場合には、「後遺障害」として認定を受けることで、障害補償給付を受けることができます。
後遺障害は、症状の程度に応じて1級から14級までの等級に分かれており、等級に応じて給付金の額も大きく異なります。
たとえば、1級違うだけで100万円以上の差が出ることもあります。
このため、正しく等級認定を受けることは極めて重要です。
後遺障害の認定手続きとは
後遺障害の等級認定は、労働基準監督署(労基署)が行います。
提出された書類や調査内容に基づいて、障害の有無や等級が判断されます。
その中で最も重要なのが、医師が作成する
「障害(補償)給付請求書添付診断書」です。
この診断書には、後遺症の内容をできるだけ詳しく、正確に記載してもらう必要があります。
診断書作成の鍵は、あなた自身の情報提供
診断書を作成する医師は治療の専門家ですが、労災保険の後遺障害等級認定に精通しているとは限りません。
そのため、あなた自身が症状や困っていること、検査結果の必要性をしっかり伝えることが大切です。
具体的には…
・しびれや痛みの状態・場所・頻度
・関節の可動域(動かせる範囲)
・労働や日常生活への支障
・実施した検査結果(MRI、神経伝導検査など)
などを医師に伝え、診断書に反映してもらいましょう。
もし情報が不十分だったり、必要な内容が記載されていなかった場合、本来認定されるべき等級が認められないリスクがあります。
労基署での面談と診断書の役割
労基署は提出された診断書の内容をもとに、原則として被災者本人との面談を実施します。
(必要に応じて、医師への照会が行われることもあります。)
この面談では、現在の症状や生活への影響などが確認され、それらを踏まえて最終的な等級認定が決定されます。
つまり、診断書の内容が正確であることが、後遺障害の認定結果を左右する最大のポイントとなります。
当事務所によるサポート体制
初めての手続きに不安を感じておられる方も多いかと思います。
当事務所では、以下のようなサポートを通じて、適正な等級認定の実現を目指します。
・医師が作成した診断書の内容を専門的な視点で確認・アドバイス
・症状を正しく伝えるための面談前の事前打ち合わせ
・労基署とのやりとりや追加対応のフォローアップ
後遺障害の申請は、単に書類を提出するだけではなく、適切な準備と専門的な対応が不可欠です。
少しでもご不安な点がある場合は、お早めにご相談ください。
あなたの大切な補償をしっかりと守るため、全力でサポートいたします。