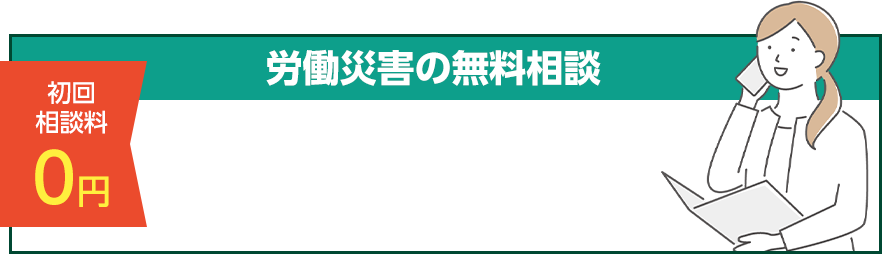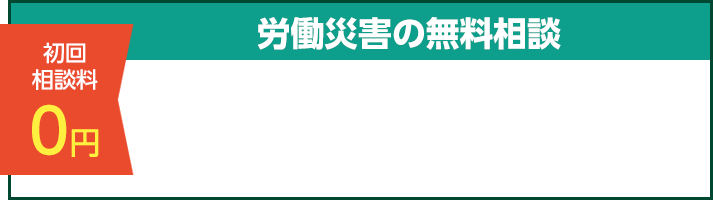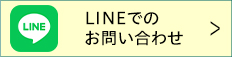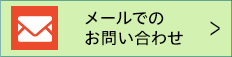労災事故が発生した場合、会社に対して損害賠償請求ができるケースがあります。
事故の発生状況により、法的根拠や請求方法が異なるため、以下で詳しくご説明します。
労災事故のタイプ
作業中に起きた労災事故は、主に次の2つに分類されます。
① 他の従業員の不注意によってけがをしたケース
たとえば、同僚がフォークリフトの運転中に被害者の存在に気づかず接触した、物を落として下にいた被害者に当たった、といったケースが該当します。
このように第三者の過失により負傷した場合は、その従業員に対する「不法行為(民法709条)」に基づく請求が可能です。
さらに、会社にも「使用者責任(民法715条)」が認められます。
つまり、従業員の業務中の過失によって他の従業員に損害を与えた場合、会社も損害賠償責任を負うことになります。
このようなケースでは、会社が比較的早い段階で責任を認め、損害賠償の話し合いに応じることも少なくありません。
・使用者責任に基づく損害賠償請求の時効は 原則3年(後遺障害の場合は症状固定から5年)です。
・ただし、安全配慮義務違反も同時に問える場合は、時効は10年となります。
② 自分一人で作業中にけがをしたケース
たとえば、プレス機での作業中に手を挟んだ、建設現場で足場から転落した、といったケースです。
このような場合は、会社の「安全配慮義務違反」に基づいて損害賠償請求をすることになります。
ただし、会社は「自己の不注意による事故であり、会社に責任はない」として、請求を拒否することが少なくありません。
これは、安全配慮義務の内容が状況ごとに異なり、明確な基準がないためです。
安全配慮義務とは?
安全配慮義務とは、労働者が安全に働けるよう会社が必要な配慮・対策を講じる義務です。
その具体的な内容は、次のような要素によって判断されます:
・業種や作業内容
・作業環境
・被災者の職位や経験
・当時の技術水準 など
一般的には、以下のようなケースでは、会社の安全配慮義務違反が認められやすいといえます。
・教育不足が原因で事故が起きた場合
・会社が管理する設備や機械に問題があり、それが事故原因となった場合
・労働安全衛生法や関連規則に違反している場合
一方で、たとえば「階段で転倒した」など、日常生活でも起こりうる事故については、会社の責任を問うのは難しいケースもあります(※ただし、労災保険の対象にはなります)。
・労基署が調査を行い、法令違反で是正勧告を受けた場合や、刑事処分が科された場合には、安全配慮義務違反が認められる可能性が高まります。
・この請求の時効は 10年 です。
請求のための具体的な手続き
会社に対して損害賠償請求が可能と判断された場合、以下の流れで対応します。
① 資料の収集
まずは、事故状況を把握できる資料(写真、報告書など)を準備します。資料が手元になくても、相談は可能です。
② 労災関係資料の取得
労災に関する資料は、労働基準監督署を管轄する「労働局」に対して、保有個人情報開示請求を行うことで取得できます(申請から約1か月程度かかります)。
③ 損害額の算出
資料をもとに、事故状況・後遺障害の等級などを踏まえて損害額を計算します。
④ 会社への通知
計算結果に基づき、内容証明郵便で通知書を送付し、会社と交渉を行います。
⑤ 話し合いで解決しない場合は訴訟へ
示談が成立しない場合は、訴訟を提起することになります。
ご相談ください
会社に対して損害賠償請求が可能かどうか判断が難しい場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
事故の内容や状況を詳しくお伺いしたうえで、適切な対応方法をご提案いたします。